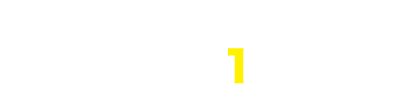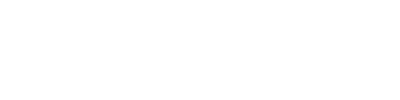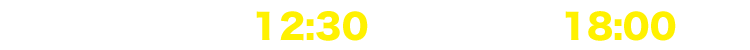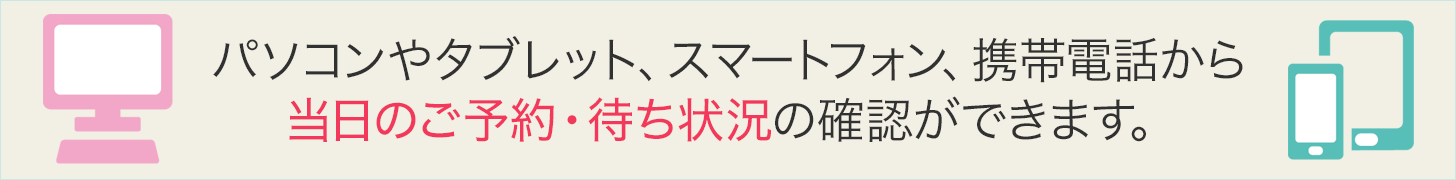病院からのお知らせ
水虫の悩みは皮膚科医へ。梅雨時期の予防策も忘れずに
水虫は、白癬(はくせん)菌という真菌(カビ)が足に感染することで発症し、水疱やかゆみなどの症状が起こる病気です。水虫の原因となるカビは、ご存じのとおり高温多湿を好むため、梅雨時から夏にかけてのこの季節は水虫の発症が増えたり症状の悪化が進んだりしやすくなる時期です。
まずは正しい予防法を知り、足を清潔に保つよう心がけましょう。
水虫を予防するポイント
- 毎日足を洗う
白癬菌の感染には24時間以上かかるため、どこかで菌が付着したとしても、毎日の入浴やシャワーで身体を清潔にしていれば感染を予防することができます - 足元が蒸れない工夫を
靴や靴下の中が蒸れている状態が続くと白癬菌が繁殖しやすいため、通気性の良い靴下を選んだり、サンダルなどを履いたりして、蒸れない工夫をしましょう - スリッパや足拭きマットの共用に注意
水虫のおもな感染経路は、水虫の人が使用したスリッパやバスマットなどを介して皮膚に白癬菌が付着することです。家族に水虫の人がいる場合や、スポーツジムやプール、銭湯などを利用する際はスリッパ等の共用を避け、帰宅したら必ず足を洗うようにしましょう
なお、水虫はほとんどが家庭内感染といわれています。
そのため、家族に水虫の人がいる場合は、その水虫を治すとともにこまめな掃除を心がけて家庭内に存在する白癬菌を取り除くことが大切です。
水虫のおもな症状
水虫にはおもに3種あり、できる場所や症状に特徴があります。
- 趾間型(しかんがた)
足の指の間に症状が出ます。赤みや小さな水疱ができ、やがて皮膚がふやけたように白くなります。その後、ぽろぽろと剥がれ落ちるようになる「乾燥型」と、患部がジュクジュクする「湿潤型」があり、水虫の中で最も多いタイプです。強いかゆみを伴うこともあり、高温多湿の季節に悪化する傾向があります - 小水疱型(しょうすいほうがた)
足の裏に小さな水疱ができ、やがて皮がむけます。強いかゆみを伴うこともあります。趾間型と同じく高温多湿の季節に悪化する傾向があります - 角質増殖型(かくしつぞうしょくがた)
足の裏全体が多少赤味を帯び、皮膚が分厚く硬くなり、ひび割れをしたり、白く乾燥して皮膚がむけたりします。かゆみを伴わないため、水虫と気づかないケースもあります。冬場は角質化した部分がひび割れて痛みが出ることがあります
水虫に関連して起こる白癬症
また、水虫に関連して発症する次のような白癬症もあります。
- 手白癬(手水虫)
手にできる白癬のことで、手水虫とも呼ばれます。手のひらにかゆみのある小さな水疱ができ、皮がむけることもありますが、皮膚が分厚くなることが多いです。単体で発症することは稀で、足白癬を掻くことによって手にうつって発症するケースがほとんどです - 爪白癬(爪水虫)
爪にできる白癬です。爪の先端あるいは爪の脇から進行することが多く、爪は白から黄色に濁ってきます。進行すると爪自体が分厚く変形します。年齢とともに発症率が高くなる傾向があります

ちなみに、手指や手のひら、足底に透明で小さな水ぶくれができる汗疱(かんぽう)や、手のひらや足の裏に水疱がくり返しできる掌蹠膿疱症(しょうせきのうほうしょう)といった、水虫によく似た症状が起こる病気もあります。
水虫は他の皮膚疾患との見分けが難しいため、水虫と思っていてもこうした皮膚症や湿疹だったというケースは少なくありません。市販の水虫薬による誤った治療法で症状を悪化させることもあるため、自己判断はせずに皮膚科の受診をおすすめします。
また、角質増殖型の水虫や、爪白癬(爪水虫)は、市販の外用薬では治療することができません。内服や、医療機関専用の塗り薬での治療が必要となるため、まずは皮膚科を受診することが大切です。
当院でも、水虫の診断や治療を行っていますので、水虫かな?と思ったら一度当院へご相談ください。
水虫の症状や診断等についてくわしく紹介された、こちらのページもご覧ください。
最新の病院からのお知らせ
- 2026/1/1 今年の花粉量は例年よりやや多い見込み。本格的なシーズン前に、早めの対策がおすすめです
- 2025/12/4 年末年始の診療のご案内
- 2025/12/1 130超えたら要注意。生活習慣の改善で高血圧を予防しましょう
- 2025/11/25 12月1日(月)よりweb予約の予約方法が変わります
- 2025/11/1 50歳を過ぎたら帯状疱疹にご用心。ワクチン接種も有効な予防法です